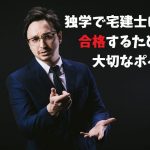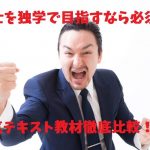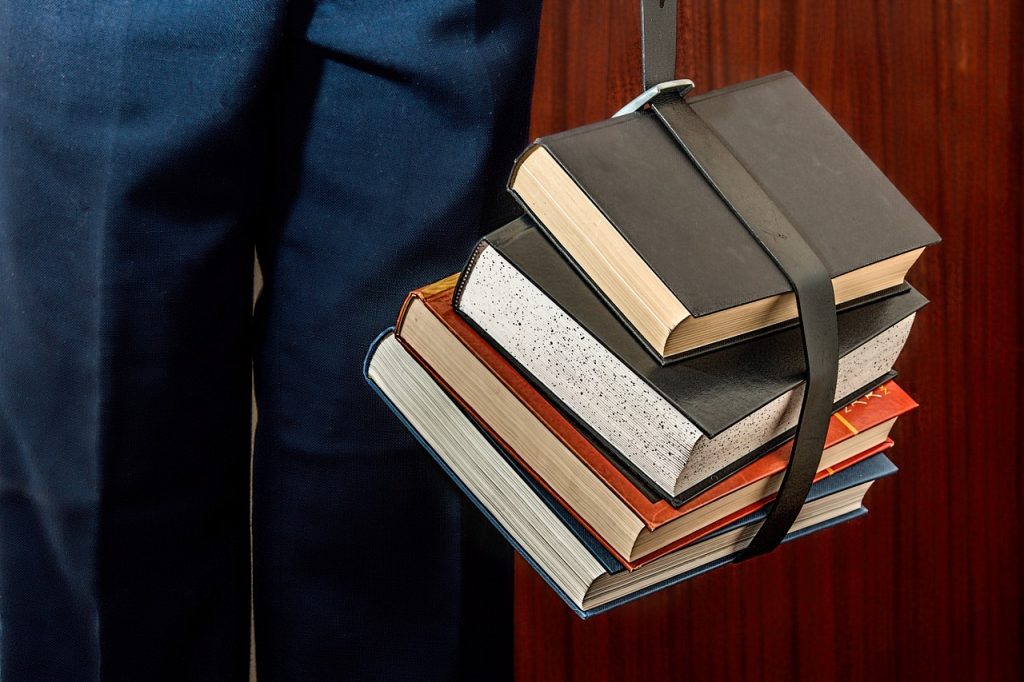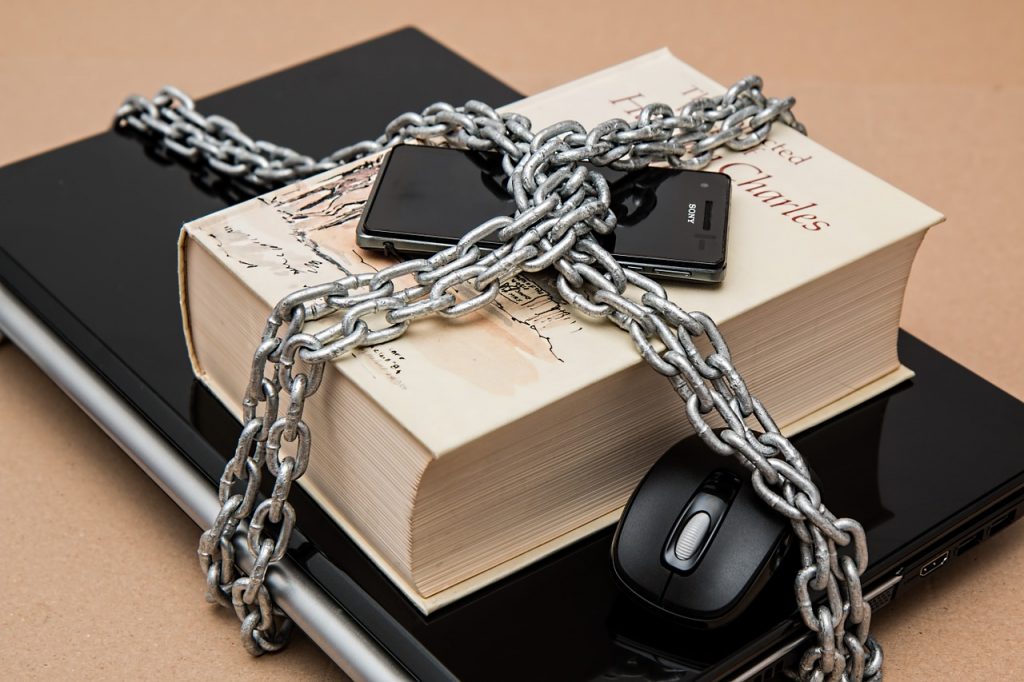宅建士試験は国家試験としてはさほど広い範囲ではないので、いくつかの科目にわけて学習を進めることで、効率的に合格することができます。
今回は以下の4つの科目を順番にご紹介し、攻略ポイントを解説します。
かんたん説明
☆宅建士試験主要4科目
■ 権利関係 → 合計14問
■ 宅建業法 → 合計20問
■ 法令上の制限 → 合計8問
■ 税・その他、免除科目 → 合計8問
計50問 / 合格ラインは33点~36点で毎年変動します
この記事だけでは書ききれないので、各段落のリンクから気になる科目の詳細を確認してくださいね。
目次
権利関係

権利関係からは毎年14問出題されますが、そのうち10問は民法分野からの出題です。
法は全ての法的な判断の基本となるべき部分なので、宅建に合格を目指す場合は民法学習から進めることをオススメします。
民法科目全般の攻略のコツ
民法は非常に範囲の広い法律ですが、宅建業法で問われる部分は絞られてきます。
基本的に不動産の取引とかかわりのある部分から出題されるので、そのあたりを念頭に問題に取り組むと良いでしょう。
かんたん説明
■ 全ての取引の根本的部分である「契約」を理解する → すべての取引は契約によって成立します。宅建試験では取引を契約と考え、法的な制度を当てはめることができる思考力が求められます。
■ テキストをしっかり読み込もう → 民法は毎年異なるモデルケースを提示して出題されるので、暗記するだけでは解けません。柔軟な思考ができるように、テキストと問題集をバランスよくインプットすることが重要です。
■ 法的な用語を理解する → 民法は善意や悪意、詐欺や強迫といった用語が登場します。ただし、これらの用語は一般的な意味とは異なる法的な意味を持った用語なので、それらの違いを把握することが大切です。
特別法の攻略のコツ
かんたん説明
■ 民法との関係を明確に → 特別法は民法に優先して適用される「特別ルール」です。民法の規定を重なった場合は、特別法が優先されると言う部分を意識して学習しましょう。民法と特別法の規定が曖昧だと、引っ掛け問題の餌食です。
■ なぜ特別法が作られたかを理解する → 特別法は無意味に作られるものではなく、必ずそこに理由(例えば、借主と貸主では力関係が違う等)があります。試験ではその理由を直接問う出題はありませんが、判断材料になるので覚えておきたい部分です。
-

-
権利関係(民法)独学のコツ Part1【宅建士】
-

-
権利関係(民法)独学のコツ Part2【宅建士】
宅建業法

宅建業法は合計20問からなる、合格のキモとなる部分です。
多くの参考書や攻略サイトで言われていることですが、宅建業法の知識が不十分だとまず合格できません。
このことを意識して、時間をかけて学習しましょう。
問題集を中心に
宅建業法からの出題は、大半が過去の焼き直し問題です。
覚えるべきことが少なく簡単なので、テキストを一読したらすぐ問題にチャレンジするべきです。
問題を繰り返すうちに思考力も身についていくので、間違ってもあきらめずに取り組みましょう。
学習時間を費やそう
宅建業法は得点源とするべき科目です。
ポイント
できれば18点~満点を狙っていきたいところですから、見飽きてしまうほど過去問を繰り返しましょう。
問題を暗記してしまった方は、1問1答形式の問題集を利用するなど、形式を変えて解いてみるのも良いですよ。
慣れてきたら予想問題
過去問を暗記してしまった方は、予想問題集を購入するのも1つの手です。
とくに有名な資格学校の問題集は宅建をよく研究して作成しているので、本試験と同じ形式で解くことができます。
-

-
宅建業法独学攻略のコツ Part1【宅建試験攻略】
-

-
宅建業法独学攻略のコツ Part2【宅建試験攻略】
法令上の制限

法令上の制限は試験よりも実務で重要になる部分です。
専門知識が多く難しいことで知られる部分ですが、配点が8点もあるので気を抜くことは許されません。
科目的に複数の法律を学習する必要が求められます。
都市計画法を最初に学ぶ
法令上の制限は他の科目と比べて多くの法律を学ぶ必要がありますが、中でも最優先したい法律が「都市計画法」です。
なぜなら、都市計画法からは以下のように、他の出題法律に登場する基礎的な用語を学習することができるからです。
かんたん説明
■ 都市計画区域
■ 地域地区
■ 用途区域
簡単な法律に力を入れる
法令上の制限から出題される法律は、難易度の高いものと低いものの差が激しい点が特徴です。
とくに簡単な農地法や宅地造成等規制法は難易度が低く得点しやすいので、確実に得点したい単元です。
法令上の制限は全体的な難易度が高いので、これらの問題を落としてしまうと最悪の場合「全問不正解」もあり得ます。
-

-
法令上の制限攻略のコツ【宅建試験攻略】
税・その他、免除科目

全体的に難易度が高い科目なので、あまり無理せず他の科目が終わった後に手を付けるべき部分です。
合計8問出題されますが、満点を目指す必要はありません。
半分程度得点できれば十分なので、解ける部分を無理なく解いていきましょう。
確実に得点できる税法
税法は細かい規定が多い割に2問しか出題されず、あまり効率的な単元ではありません。
ただし、免除科目などに比べると出題点を確実に学ぶことができるので、この科目の中では優先して学習すべき部分です。
現場対応力が求められる免除科目
この部分に力を入れて学習することはハッキリ言って時間の無駄です。
範囲が広く出題形式も予想がつかないので、過去問に目を通したあとは常識的判断に従って現場対応力で取り組みましょう。
ただし、統計情報は毎年予測が可能です。
多くの資格学校で問われやすい部分を公開しているので、必ず目を通しましょう。
今回の宅建士試験の予想範囲をリンク先の記事に載せているので、気になる方は確認してください。
-

-
税・免除科目攻略のコツ【宅建試験攻略】